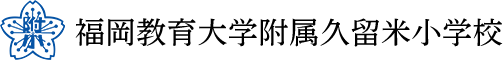研究
研究主題(令和7年度)
「自立」して学ぶ子供を育てる学習指導
ー【起こす】【進める】【つなぐ】評価活動を通してー
「自立」して学ぶ子供 とは
実生活・実社会との関わりの中で自分にとっての学ぶ意味を見いだし、必要に応じて他者と関わり、よりよい自分や社会の実現に向かって試行錯誤しながら新たな価値を創造する子供である。本校では、「自立」して学ぶ子供を「自我関与」「共創協働」「価値追求」の三つの側面から捉えることとした 。
そして、本校の子供の実態を基に、目指す「自立」して学ぶ子供の姿を三つの側面から具体化した 。
○ 自分にとっての学ぶ意味を見いだす(自我関与)
そして、本校の子供の実態を基に、目指す「自立」して学ぶ子供の姿を三つの側面から具体化した 。
○ 自分にとっての学ぶ意味を見いだす(自我関与)
・内発的動機や当事者意識を基に、自ら対象と関わり、自分にできることを選択・決定すること。
・自己の成長を自覚し、達成感や充実感をもって次の学びにつなげようとすること。
○ 必要に応じて他者と関わる(共創協働)
・他者と対話を重ね、自分の視点を広げ深めたり、考えを多面的・多角的に捉えたりすること。
・他者を尊重し、必要に応じて援助を求め合いながら、共通の目的に向かって協働すること。
○ よりよい自分や社会の実現に向かって、試行錯誤しながら新たな価値を創造する(価値追求)
・知識や技能、学び方を活用し、試行錯誤を通してよりよい解決や在り方を追求すること。
・学習したことを基に、他の学習や生活、社会に生かそうとする価値を創りだすこと。
研究主題(令和6年度)
AIが進展する現在、求められる学びとして
「自立」して学ぶ子供を育てる学習指導
ーICTを活用した相互評価活動を中心にー
本校研究の歩み(研究主題とその内容)
| 昭和21年 | 〇新教育の計画と展望 |
|---|---|
| 昭和24年 | 〇久留米プランの構想と展開 ・総合生活学習の構成 |
| 昭和25年 | ・分化生活学習単元の構成と展開 |
| 昭和26年 | ・久留米プランに基づく学習指導の実証的研究 |
| 昭和27年 | ・学習指導の実証的研究-学習指導の能率化-(久留米プランに基づく) |
| 昭和28年 | ○生活教育に立つ学習指導の反省と進路 ・小中学校の関連における進路とその対策 |
| 昭和29年 | ○教育計画の改新と有機的運営 |
| 昭和30年 | ○学習指導過程の実践的研究 |
| 昭和31年 | ○学習指導過程の実践的研究 |
| 昭和32年 | ○学習指導過程の問題点とその解明 |
| 昭和33年 | ○転換期における小学校の教育 |
| 昭和34年 | ・教育目標の検討 |
| 昭和35年 | ・改訂指導要領の検討と指導法の改善 ・教育課程の方法的検討 |
| 昭和36年 | ○教育的系統に立つ学習指導の実証的研究 |
| 昭和37年 | ・発達系統の再認識と学習指導の深化 |
| 昭和38年 | ・教材系統の再検討と学習指導の効率化 ・効果を高める学習指導の方途 |
| 昭和39年 | ○主体性の確立をめざす学習指導の体制化 ・指導過程を中心に |
| 昭和40年 | ・学習形態を中心に |
| 昭和41年 | ・主体性を育てる学習指導の体制化 |
| 昭和42年 | ○創造性を育てる学習指導 |
| 昭和43年 | ・子どもの実態に立つ学習過程を中心に |
| 昭和44年 | ・教材の変形に基づく学習過程 ・創造的活動を旺盛にする学習過程 |
| 昭和45年 | ・「ひとりひとりが情報を生かす学習」の指導法賂 |
| 昭和46年 | ・「情報を階層的に生かす学習」の指導法略 |
| 昭和47年 | ・三層三段階の学習過程の体制化 |
| 昭和48年 | ○創造的学び方を育てる学習指導 |
| 昭和49年 | ・創造的活動を旺盛にする学習法賂の探究 |
| 昭和50年 | ・創造的な学び方を形成する指導法賂 ・考え方や行為の強調をはかる学習過程 |
| 昭和51年 | ・考えや行為の社会化をはかる学習活動 |
| 昭和52年 | ○対話的思考を育てる学習指導 |
| 昭和53年 | ・出会いの階層的深化を求めて ・出会いを階層的に深める学習過程 |
| 昭和54年 | ・個が生きる出会いの深化 |
| 昭和55年 | ○自己が豊かにつくりだす学習指導の創造 |
| 昭和56年 | ・対象へ生き生きと働きかける活動づくり |
| 昭和57年 | ・見直しながら問いつづける活動を通して ・思考を深める操作学習を求めて |
| 昭和58年 | ○自ら工夫しつづける子どもを育てる学習指導 |
| 昭和59年 | ・考えを組み立てていく活動を求めて |
| 昭和60年 | ・考えをつくりかえる学習活動を求めて ・思考力を高める操作学習を求めて |
| 昭和61年 | ○自ら表現豊かに学ぶ力を育てる学習指導 |
| 昭和62年 | ・個の持ち味を生かした追求活動を求めて |
| 昭和63年 | ・個の持ち味を伸ばす学習活動を求めて ・個が生きる表現活動を求めて |
| 平成元年 | ○自己を豊かに創造する子どもを育てる学習指導 |
| 平成2年 | ・経験を生かす体験的活動を求めて |
| 平成3年 | ・経験を組織化する体験的な活動を求めて ・体験的活動の授業づくり |
| 平成4年 | ○主体的に対応しつづける子どもを育てる学習指導 |
| 平成5年 | ・学習体験を創造する過程の構成を求めて |
| 平成6年 | ・学習体験を豊かにする活動の多様化を求めて ・「支援システム」による授業づくりを求めて |
| 平成7年 | ○自己の可能性をひらく子どもを育てる教育 |
| 平成8年 | ・思考・判断の多様,多面を求めて |
| 平成9年 | ・学習対象の特性にふれる具体的方策を求めて ・子どもが生きる学習環境を求めて |
| 平成10年 | ○生きる力を育む教育の創造 |
| 平成11年 | ・課題を生み出す活動構成のおり方 |
| 平成12年 | ・課題解決を楽しむ活動構成のおり方 ・「基礎的・基本的な学力」が身につく課題解決活動 |
| 平成13年 | ○「基礎的・基本的な学力」を自ら高める教育の創造 |
| 平成14年 | ・メタ認知の働きを生かした振り返り活動を通して |
| 平成15年 | ・メタ認知の働きを豊かに生かす発展的活動を通して ・メタ認知を生かした授業改善への道 |
| 平成16年 | ○未来志向の学びをつくる授業の展開 |
| 平成17年 | ・「基本の学び」から「発展の学び」への活動構成の工夫を通して |
| 平成18年 | ・相互作用を位置付けた「基本の学び」から「発展の学び」への活動を通して ○「わかる・できる」「使いこなす」 子供を育てる基本の授業・応用の授業 |
| 平成19年 | ○生涯学力の基礎を育む授業の創造 |
| 平成20年 | ・自力活動と協働活動の有機的構成を通して ・思考を深める自力活動と協働活動を通して |
| 平成21年 | ○学びの知恵をはぐくむ授業の創造 ・言語活勣による思考・表現の活性化を求めて |
| 平成22年 | ○知的思考をはぐくむ教育活動の創造 ・各教科等における言語活動の具体化を求めて |
| 平成23年 | ○知的に考える子どもを育てる教育活動の創造 ・言語活動を生み出す場づくりを通して |
| 平成24年 | ○「協同的学び合い」をつくる言語活動 ・教科の特質をふまえた授業づくりを通して 文部科学省研究開発学校指定 |
| 平成25年 | ○「情報編集力」を育てる教育課程の創造 ・情報科を要とした各教科等の学習のあり方を通して |
| 平成26年 | ○21世紀を生き抜く子どもを育てる教育の創造 ・情報編集力を働かせる活動の工夫 |
| 平成27年 | ○主体的に学びを生み出す子どもが育つ学習 ・情報を編集する活動の工夫を通して |
| 平成28年 | ○主体的に学ぶ子どもが育つ学習 ・見方・考え方を働かせる活動を通して |
| 平成29年 | ○主体的に学び続ける子供を育てる学習指導 ・見方・考え方を働かせる操作活動を通して |
| 平成30年 | ○深く学ぶ子供を育てる学習指導 ・見方・考え方を働かせる表現活動を通して |
| 令和元年 | ○深く学ぶ子供を育てる学習指導 ・見方・考え方を働かせる表現活動を通して |
| 令和2年 | ○深く学ぶ子供を育てる学習指導 ・見方・考え方がつながる活動構成を通して |
| 令和3年 | ○豊かな時代を切り拓く子供を育てる学習指導 ・ICTを基盤とした「目的」「選択」「調整」「省察」のサイクルを通して |
| 令和4年 | ○豊かな時代を切り拓く子供を育てる学習指導 ・スタディ・ログを生かした再構成活動を通して |
| 令和5年 | ○豊かな時代を切り拓く子供を育てる学習指導 ・スタディ・ログを用いた学習としての評価活動を通して |